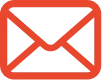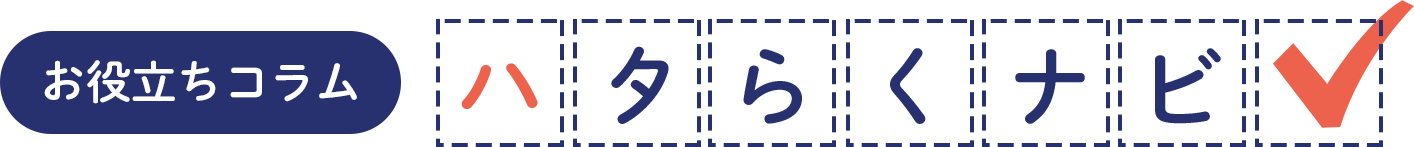カテゴリーから知りたい情報を探す
- 障害年金 (2)
- 就活HACK (8)
- 合理的配慮 (18)
- 法律 (1)
- 特例子会社 (4)
- 就労移行支援事業所 (10)
- 障害者雇用 (29)
- クローズ就労 (9)
- オープン就労 (13)
- はたラクHACK (15)
- 自閉症スペクトラム障害(ASD) (27)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD) (31)
- 限局性学習障害(SLD) (12)
記事一覧
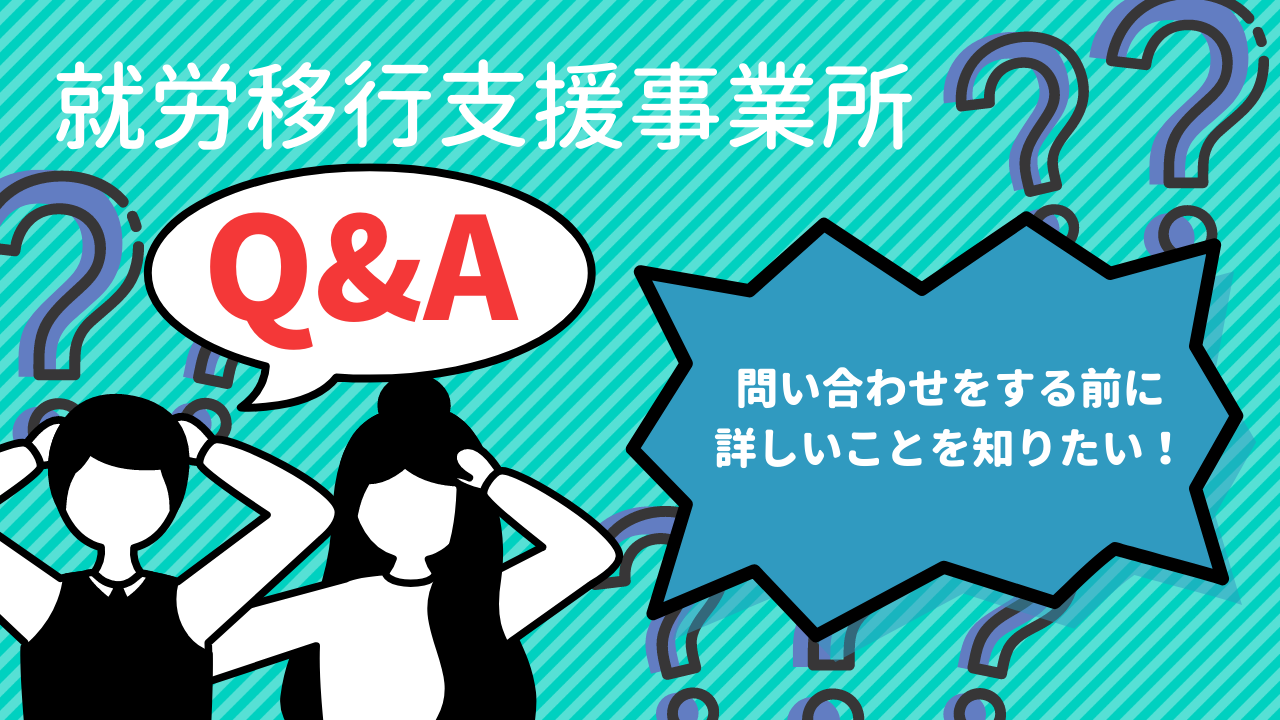
就労移行支援に興味があるけど、問い合わせをする前に詳しいことを知りたい!といった方に向け、就労移行支援事業所ディーキャリアに多く寄せられるご質問をまとめました。

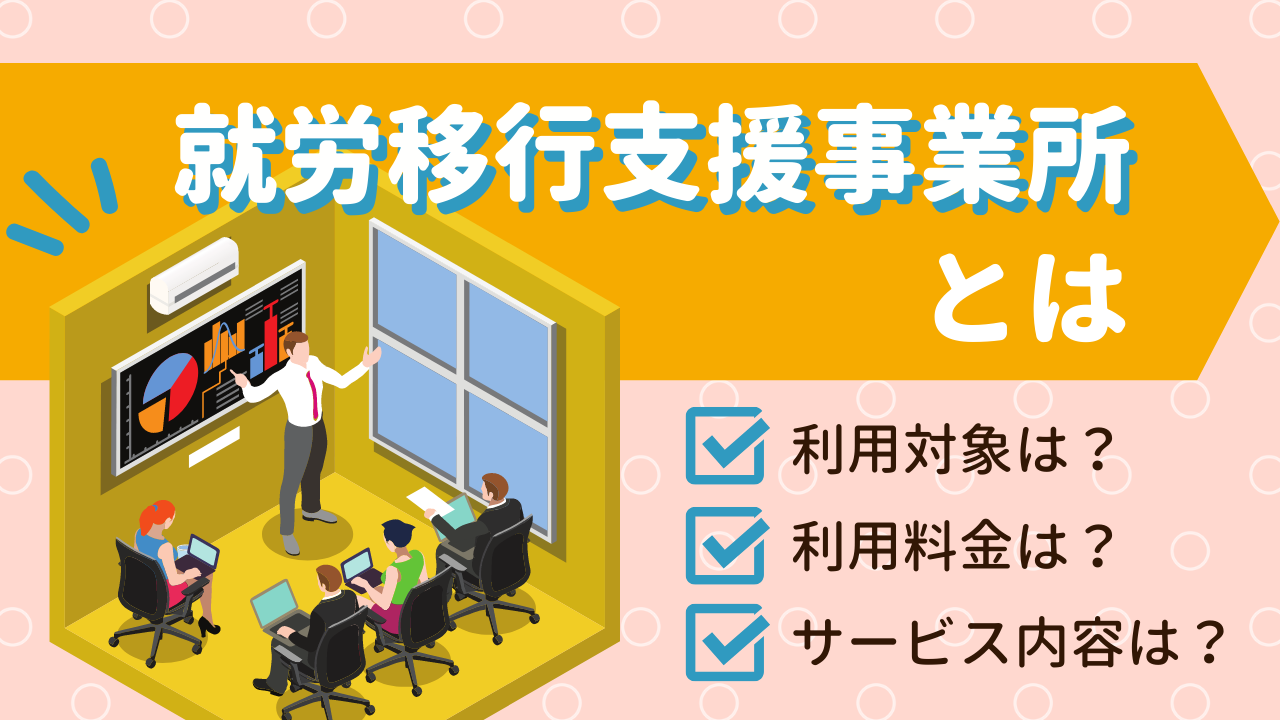
障害のある方が「働く」ことへの不安やお悩みを抱える方をサポートする、障害福祉サービスの「就労移行支援事業所」。利用対象や利用料金、サービス内容などの基本情報を紹介しています。


「合理的配慮」に詳しく知りたい方に向け、よくあるご質問形式で補足情報をまとめました。
- タグ:
- 合理的配慮

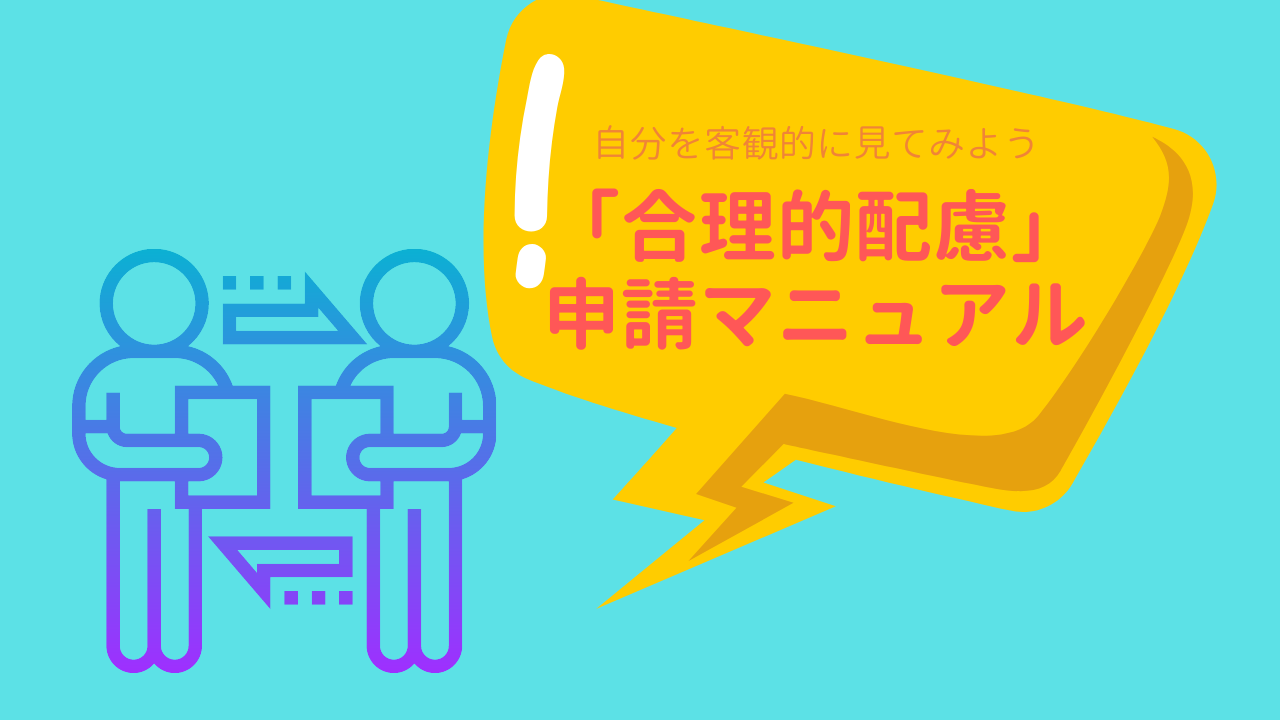
合理的配慮を依頼したいけど、どうやって勤務先に伝えればいいの?対応してもらるか不安… といった方に向け、4つのステップに分け、申請方法をまとめました。
- タグ:
- 合理的配慮

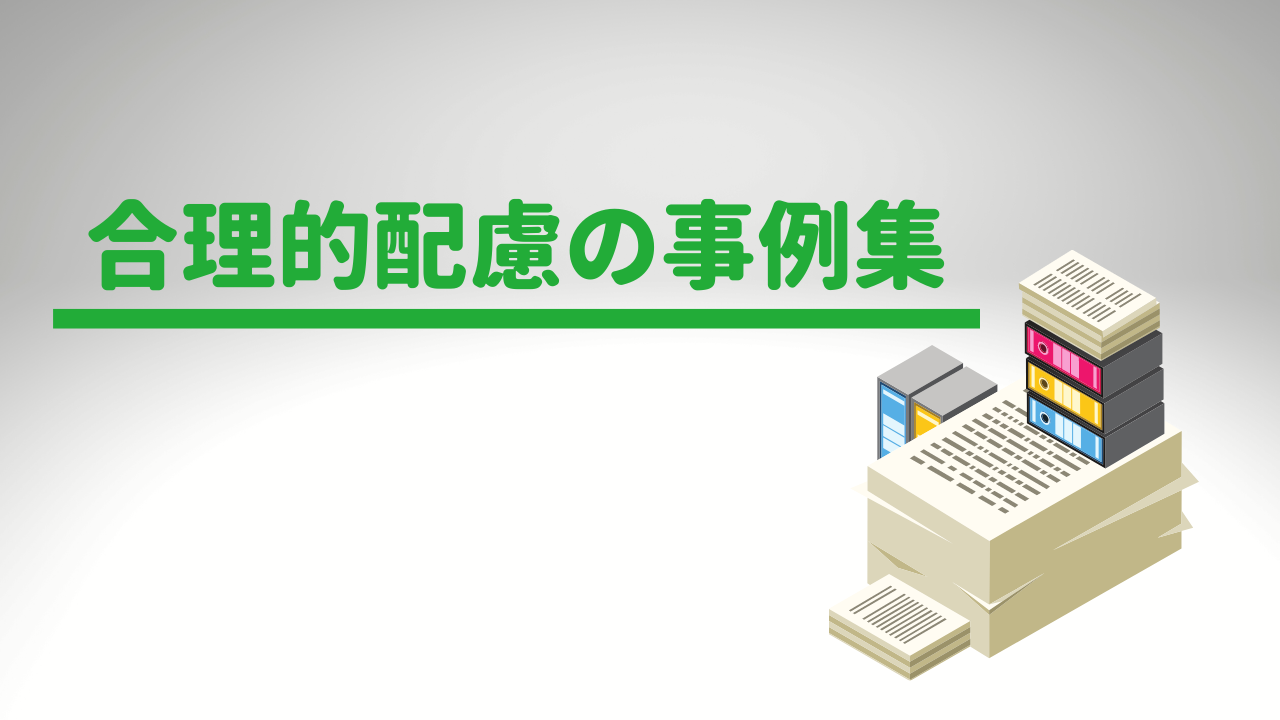
実際に企業が提供している「合理的配慮」の事例をまとめました。 「仕事上の困難さ」に対する配慮内容をケースごとに紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
- タグ:
- 合理的配慮

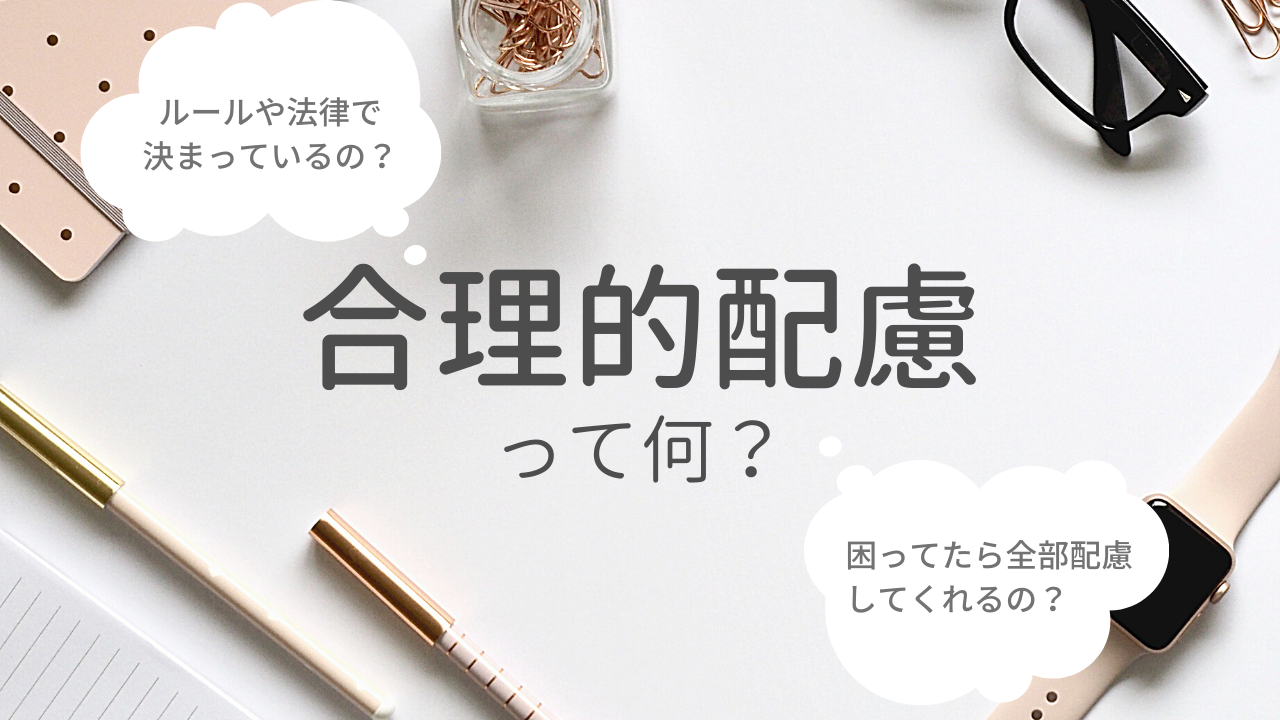
障害による困りごとへの配慮を雇用先に求めることのできる「合理的配慮」。 自分は対象となるのか?どんな制度なのか?といった疑問にお答えするための基礎情報をまとめました。
- タグ:
- 合理的配慮

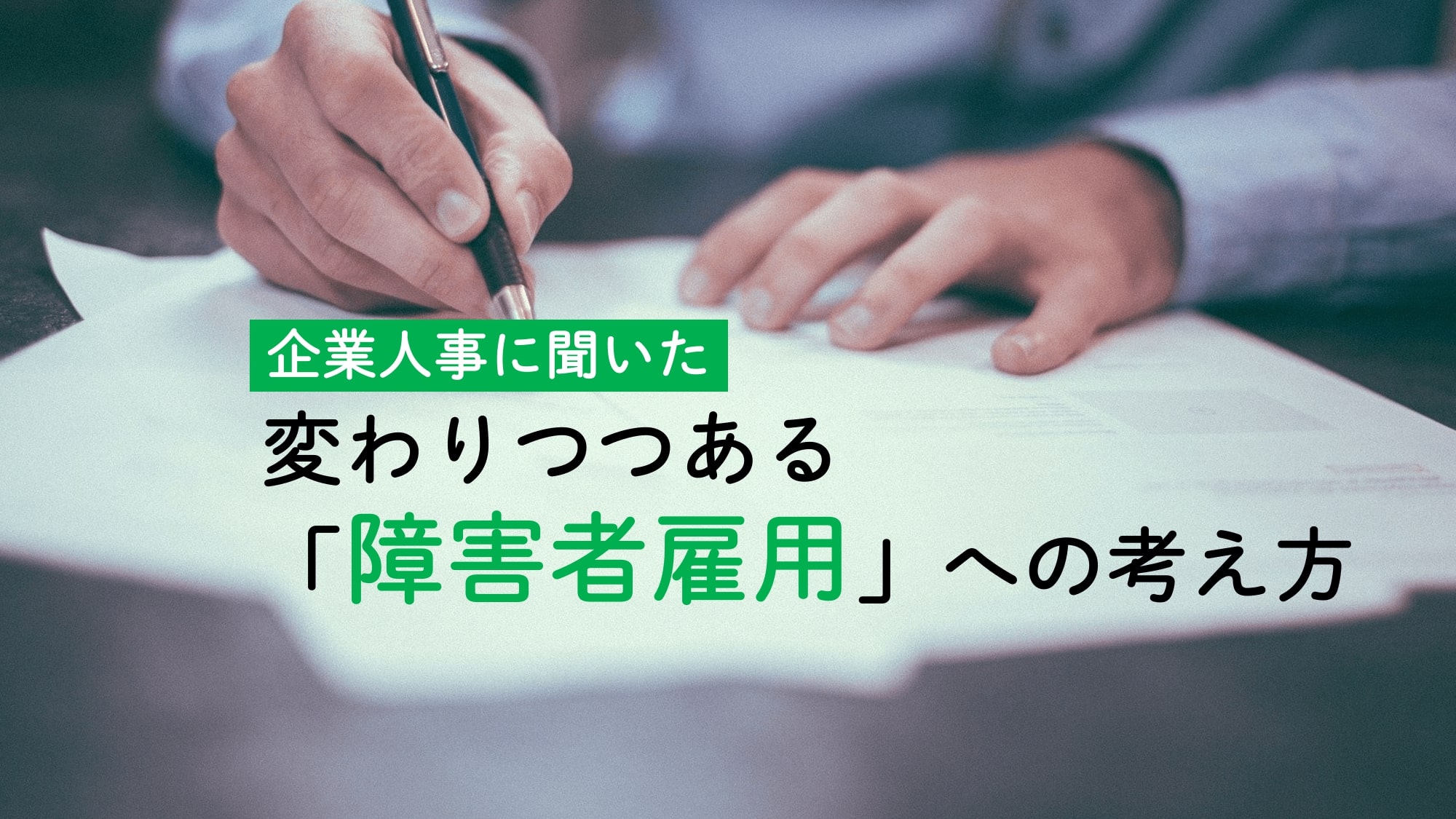
最近、障害のある人が働きやすくなったって聞くけど本当?障害者雇用担当者のリアルな声をまとめました。

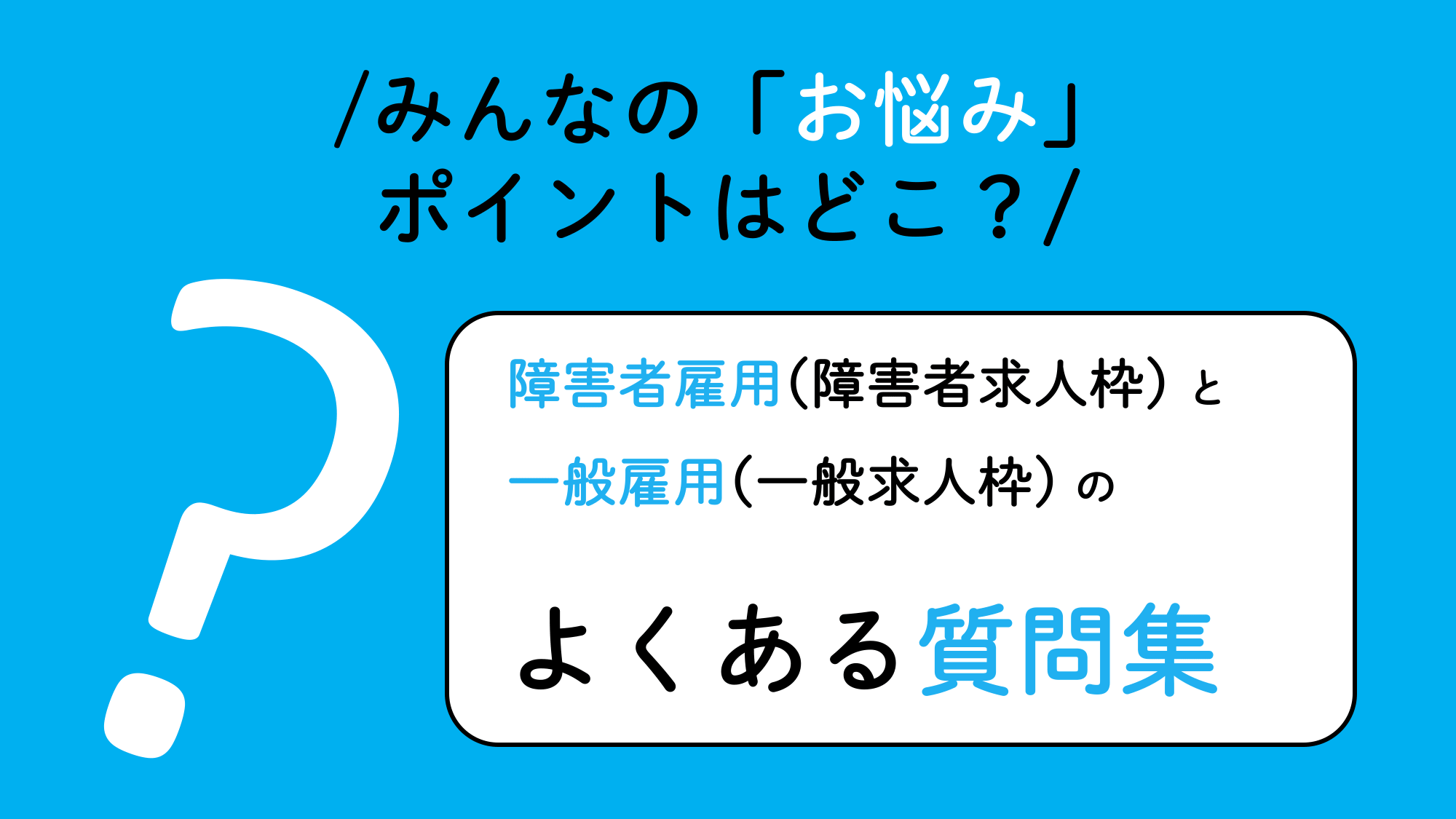
発達障害のある方が就職活動をはじめるときに、知っておくべき知識を、よくある質問形式でまとめました。

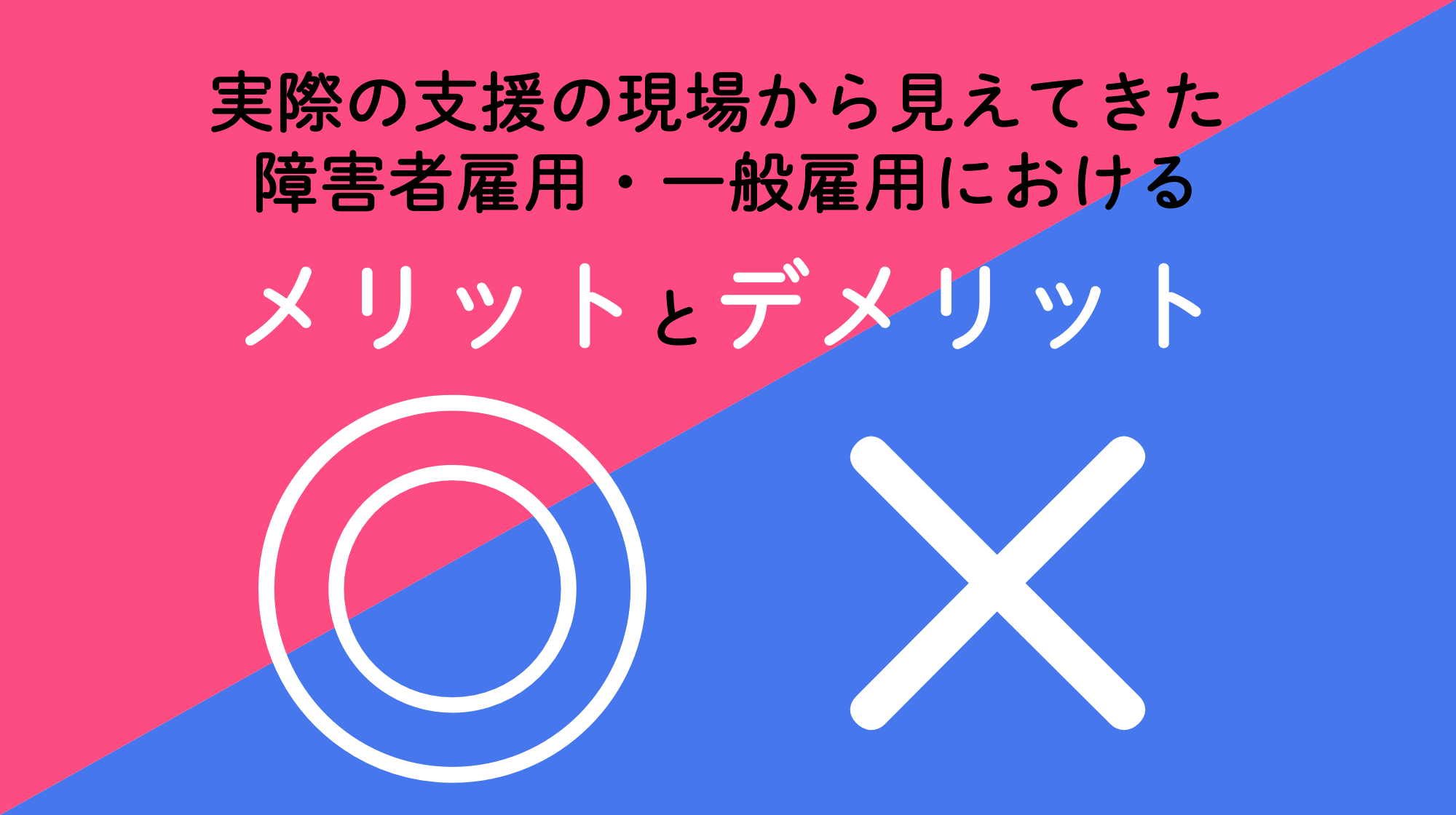
障害者枠・一般枠には、それぞれメリットとデメリットがあります。良い面、もしくは悪い面だけではなく、両方を知ることにより、自分が目指したい働き方と照らし合わせてみることができます。

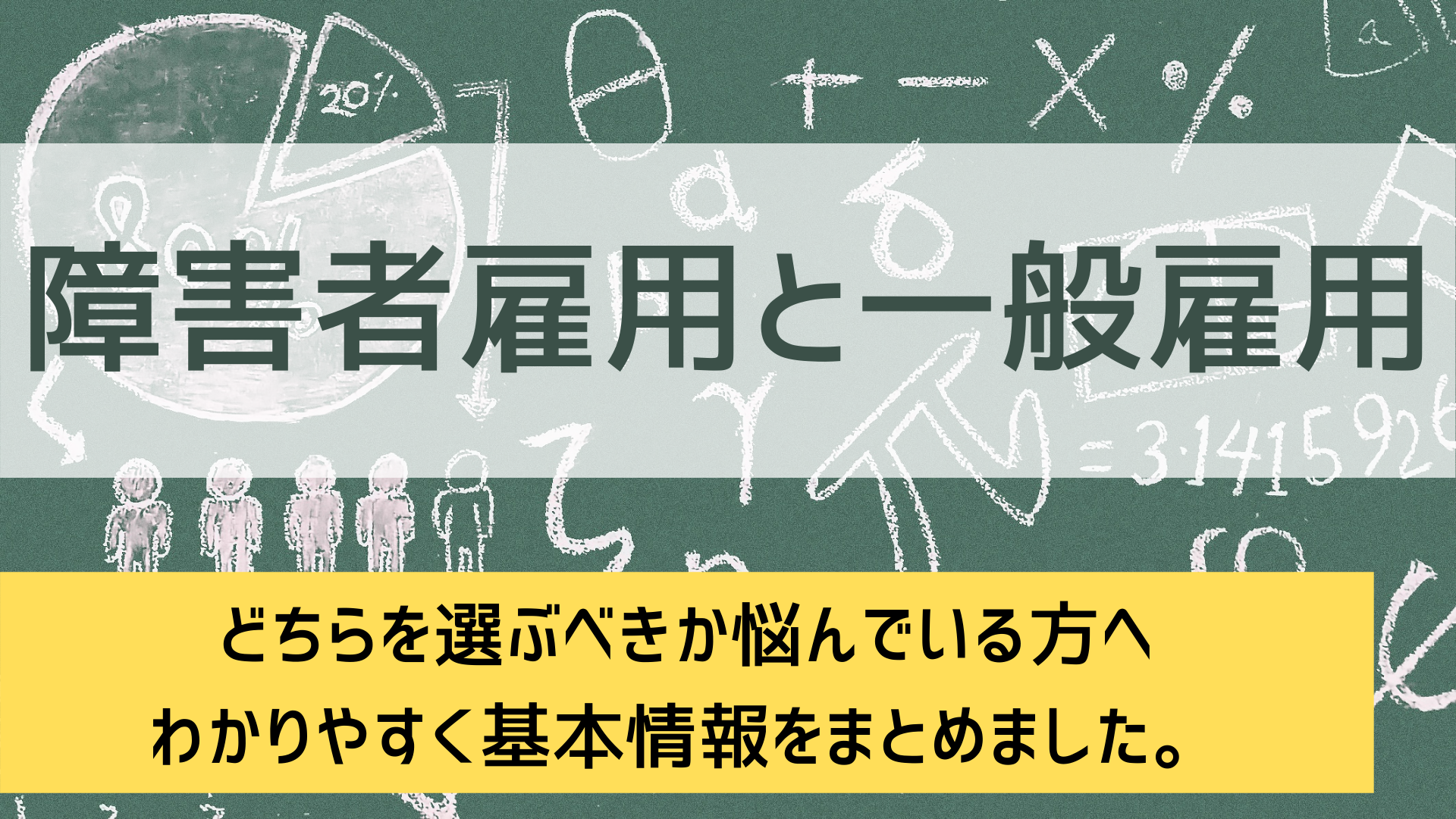
「障害者雇用」「一般雇用」「オープン」「クローズ」それぞれの基本情報を分かりやすくまとめました。どのような違いがあるのか、選ぶポイントはどこにあるのかについて説明しています。