就労移行支援事業所ってどういうところ?
就労移行支援事業所が何なのかよくわからない!という方へ。
どんなサービスなのかを詳しくご説明しております。
どんなサービスなのかを詳しくご説明しております。
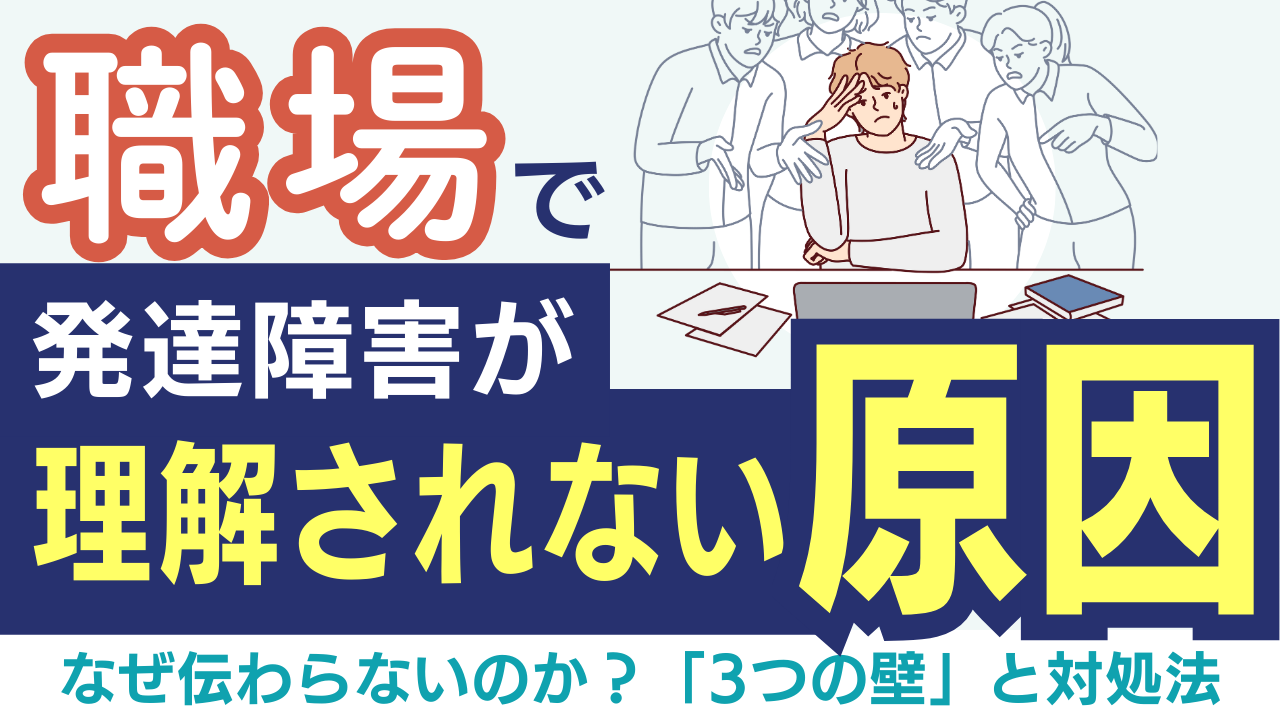
職場で発達障害が理解されないのはなぜ?原因と誤解を減らすための対処法、心が楽になるマインドセットをADHD当事者の経験を交えて紹介します。


「嫌われている?悪口を言われているかも」…その不安、ASDの特性によるものかもしれません。原因と対処法について発達障害当事者が解説。


ADHD当事者の筆者が、診断を受けたあとの行動ステップ、利用できる制度、職場への伝え方、自己理解・特性への工夫までを解説します。

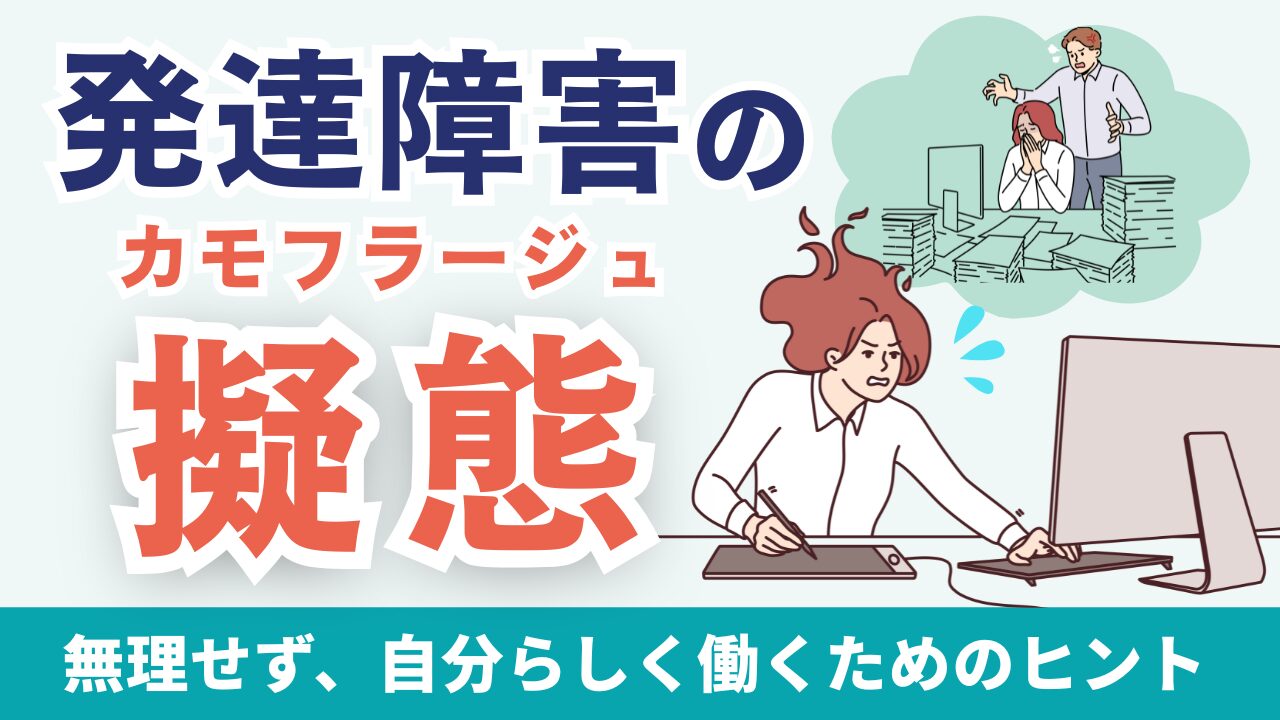
周囲に馴染むために本当の自分を隠そうとする「擬態」についてADHD当事者が解説。無理に特性を隠すことで起こるリスクや対処法について紹介。

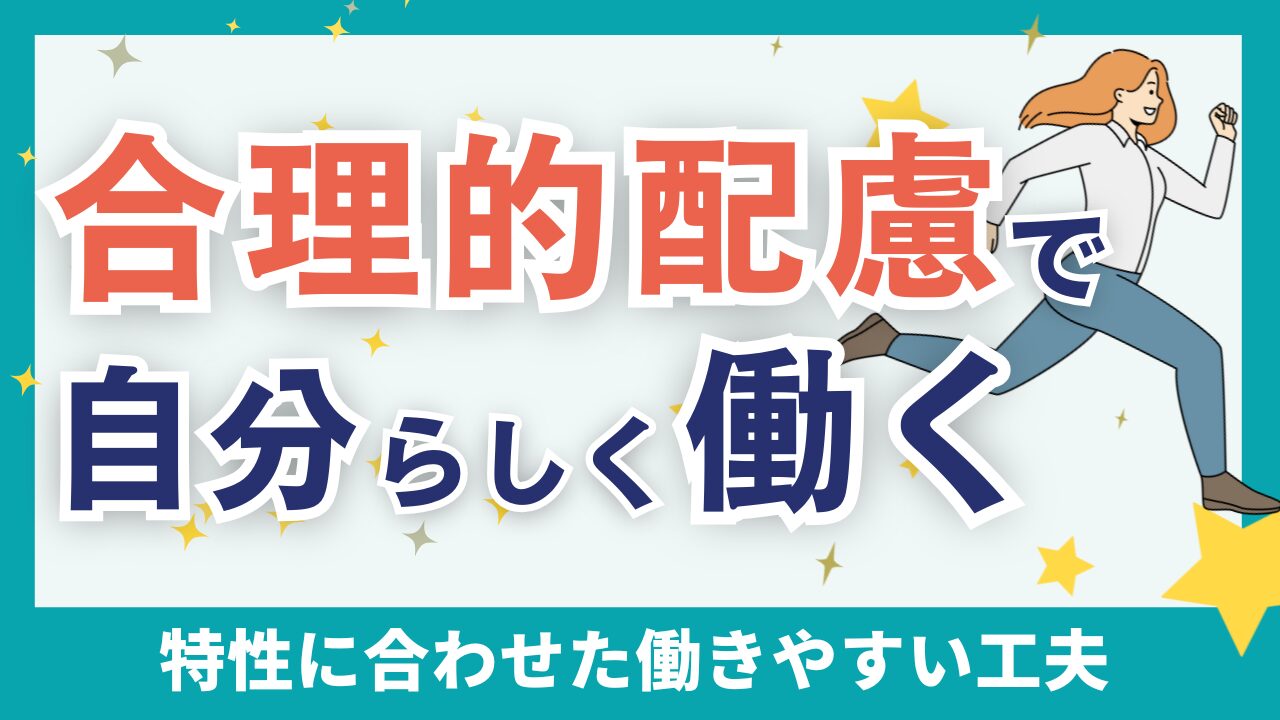
2024年4月から職場での「合理的配慮」が法的義務になりました。自分らしく無理なく働くためには、自分に合った配慮を見つけることが大切です。


なぜ事務が苦手?どうすれば働きやすくなる?ADHD特性で事務作業が苦手な方に向け、見える化・仕組み化など実践的な仕事術を紹介します。
