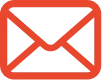【境界性知能と発達障害とは?】自分らしい生活を送るためにできること
みなさん、こんにちは。
ディーキャリア芝浦オフィスの馬場です。

「境界性知能」という言葉を耳にしたことはありますか?
なかには、「自分もそうなのかもしれない」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
境界性知能や発達障害のある方の多くは、日常生活や仕事で困りごとを抱えていることがあると言われています。
その困りごとと向き合うには
自分に合った工夫をしたり、必要に応じて支援を受けるためにできることが必要になってきます。
この記事では境界性知能について理解を深め、より自分らしく生活するための方法を考えてみましょう。
●記事を書いた人:馬場(生活支援員/社会福祉士)
2024年4月 デコボコベース株式会社入職。
前職では小売業の店舗マネージャーとして、店舗運営や人材育成に従事。
心身のバランスを崩してしまい、職場復帰に困難を抱える方を目の前にし「困っている方の力になりたい」、「ライフワークを見つけるためのサポートをしたい」と考え障害福祉の勉強をはじめる。その後就労移行支援事業所の支援員へ転職を決意。現在はディーキャリア芝浦オフィスの生活支援員として、安定した就労のための生活面でのサポートをおこなっている。
境界性知能ってなに?
まずは境界性知能がどういうものかを見てみましょう。
境界性知能とは、知能指数(IQ)が70〜85の範囲にある状態を一般的にさします。
IQ(Intelligence Quotient)とは「知能指数」のことで、知能の高さを測るための指標です。
IQの値は、平均的な知能を持つ人を基準にして測定され、100が平均とされています。
専門的な心理検査を受けることによって、結果が出る事が多いです。しかし、この結果はあくまでその人の「知能」を数値で表したものであり、すべてを決めるわけではありません。
一般的に、IQが70未満だと「知的障害」とされることが多いですが、こちらについても診断がおりるかどうかはケースバイケースです。IQが70〜85の範囲に該当する場合、障害認定を受けることは少なく、社会的サポートが不足していることが多い現実があります。そのため、社会福祉サービスなどの支援を受けることなく、困難を感じながら生活している方が少なくありません。

実は日本では、境界性知能を持っている人は約14%もいると言われています。
この数字を聞いて、「意外と多いな」と感じる方もいるかもしれません。
正式に障害の診断を受けていない境界性知能の場合、福祉サービスを利用できないことも多く、必要な支援が受けられず、生活の中で困りごとを解決できないまま悩んでいることが多いのです。
もし、境界性知能と診断された場合、自分がどんな特性を持っているのか、そしてどんな時に、困り感を抱えているのかを分析してみることが困り感を解消するための第一歩といえるでしょう。
自己理解を深めるためには、自分一人で考えるだけでなく、周囲の人から意見をもらうことも大切です。
自分の特性を知ることで、仕事や日常生活でうまくいかないことの原因がわかり、改善策を見つける手助けになります。自分自身の特性を理解することで、自分らしい生活ができるようになるでしょう。
発達障害との関係
境界性知能が日常生活に影響を与えることがありますが、それに加えて発達障害を抱えている場合、さらに複雑な問題が生じることもあります。発達障害には、自閉症スペクトラム障害(ASD)やADHD(注意欠如多動性障害)などがあり、それぞれ特有の特性があるといわれています。
特に、この「境界性知能」と「発達障害」が併存すると、
日々の生活や仕事がうまくいかないというケースが多く見受けられます。
例えば、発達障害の特性である「注意を維持するのが難しい」「計画性がない」「対人関係で困難がある」などの一般的に多いと言われる特性が、境界性知能の特性と重なると、日常生活がさらにストレスフルになりやすいと言われています。
発達障害を持つ方は、特に感情や状況の把握がうまくいかず、コミュニケーションに苦労することがあります。一方、境界性知能があると、何が得意で何が苦手なのかを自分でうまく認識できない場合もあり、苦手なことに対しての対処や判断が難しくなることがあります。
そのため、自己肯定感が低くなりがちで、「自分はできない」「周りと違う」と感じることが増えてしまうケースも多く見受けられます。
このような状態が続くと、自己否定に繋がり、社会とのつながりが遠ざかってしまうこともあります。
実際に直面しやすい困りごと
境界性知能を持つことによって、どんな困りごとが日常生活に現れるのでしょうか?実際にどのような場面で困るのかを考えてみましょう。

仕事面
職場での指示を理解するのに時間がかかることがあります。上司から「これをやっておいて」と言われても、どこから始めれば良いのかがわからないという場面がよくあります。また、仕事が複雑だと、どう進めるべきか迷ってしまうこともあります。例えば、忙しい時期に細かい指示を受けても、それをうまく処理できず、ミスをしたり、期限に間に合わなかったりすることがあります。こういった状況が続くと、「自分は仕事ができない」と感じてしまい、仕事への自信が失われることもあります。
日常生活面
また、日常生活においても困ることがあります。例えば、友人や家族とのコミュニケーションがうまくいかないと感じることがあります。「相手の言っていることが理解できない」「自分の気持ちがうまく伝わらない」など、ちょっとした言葉のやり取りでもストレスを感じることがあります。また、買い物の際に店員の説明がうまく理解できなかったり、家事を進める順番がわからなかったりすることもあります。こうした小さな困りごとが積み重なることで、日常生活全体にストレスを感じることがあるでしょう。
自分に合ったサポートを受け、困りごとを乗り越えよう!
では、こうした困りごとをどのように解決していけば良いのでしょうか?
自分に合ったサポートを見つけることができれば、
生活が楽になり、ストレスが軽減するかもしれませんね。
①自己理解
まず最初に、自分がどんな特性を持っているのかを理解することが大切です。自分の得意なことや苦手なことをしっかり把握することで、無理をせずにうまく生活していける方法が見つける第一歩となるかもしれません。苦手なことがあれば、それに対するサポートを受ける準備ができます。
➁環境を整える
職場や生活環境を整えることも有効です。例えば、業務の進め方を細かく指示してもらったり、視覚的なツールを使ったりすることで、自信を持って作業ができるようになります。生活の中では、スケジュール管理や整理整頓をする等、他者に頼ったり周囲のサポートを受けながら過ごしやすい環境を整えていきましょう。
③支援を活用する
支援が必要だと感じたら、専門のサポートを受けることが重要です。福祉サービスやカウンセリングを利用することで、困難に対する対処法を学び、自分に合った方法を見つけることができます。また、発達障害に特化した支援を受けることで、日常生活や仕事での困りごとを減らすことができないか相談してみましょう。
実際の支援事例から学ぶ!自分に合った方法とは?
つぎに、支援を受けて生活が改善した具体的な事例を見てみましょう。
①仕事で困難を感じていたAさんの場合
Aさんは職場で業務が複雑で、指示を理解するのに時間がかかり、仕事が進まないことが多かったそうです。そこで、業務を細かく分けてもらい、視覚的なチェックリストを作成しました。
その結果、少しずつ業務を進められるようになり、自信がついてきたそうです。
➁対人関係で悩んでいたBさんの場合
Bさんは境界性知能と発達障害を持っており、職場での対人関係に悩んでいたそうです。そこで、コミュニケーションスキルを向上させるトレーニングを受け、感情のコントロール方法や自己表現の方法を訓練しました。その結果、周囲との関係構築がしやすくなったそうです。
これからの自分を作るために!前向きに一歩踏み出そう

境界性知能があることは、決して自分を制限するものではありません。
自分の特性を理解し、適切なサポートを受けることで、もっと自分らしく生活を楽しむことができます。無理に周りに合わせるのではなく、自分のペースで進んでいくことが大切です。
もし、日常生活や仕事で困難を感じることがあれば、まずはその一歩を踏み出してみましょう。
「どう支援を受ければ良いのか分からない」と感じている方も少なくないかもしれませんが、そんなときこそ、身近な相談窓口や社会資源を活用してみましょう。
実際に、身近なもだと以下のような相談窓口があります。これらの機関は、それぞれ異なる役割があります。お住まいの地域や自治体によってサービスの内容が異なります。まずは、お近くの機関を調べてみましょう。
■ 地域の基幹相談支援センター
生活全般に関する相談支援を行う機関です。主に障害を持つ方々やその家族に向けた支援を提供しており、必要な支援の調整や情報提供、他の福祉サービスとの連携を行っています。困りごとがあれば、まずはこのセンターに相談することが推奨されます。各都道府県や市区町村に設置されていることが多いです。
■ 発達障害者支援センター
発達障害を持つ方々に対して専門的な支援を行う施設です。生活支援、教育支援、就労支援などを提供し、個々のニーズに合わせたサポートを行っています。また、支援が必要な家族への相談やアドバイスもおこなっており、障害を持つ方々が社会で自立して生活できるよう支援しています。各都道府県に設置されており、支援内容については地域ごとに異なる場合があります。
■ 就労支援センター
障害を持つ方々や就職に困難を抱える方々に対して、就職に向けた支援を提供する専門機関です。利用者に合った支援プランを提供し、自立した就労を支援します。
■ 地域障害者職業センター
障害を持つ方々の就業支援等を行っている機関です。障害者雇用を推進するための企業との連携もおこなっており、障害者雇用の促進と安定した就労をサポートします。就職後の職場での定着支援もおこなっている場合があります。
■ 就労移行支援事業所
就職を目指す方々に対して、就職に向けた支援をおこなう施設です。職業訓練を提供し、自己理解を深めるとともに、仕事の技術やマナーを学びます。また、実際の企業での実習などを通じて、実務経験を積むことができる場合もあります。就職後のサポートもおこなっており、就労継続支援を提供している場合もあります。ディーキャリアもこの就労移行支援事業所です。
■無料見学会に来てみませんか?

「自分の特性を理解したり、対策を立てられるようになりたい!」
「得意・不得意を知りたい」「周囲の人の考え方、他者視点を学びたい!」
と感じた方は、
ぜひディーキャリア芝浦オフィスの無料体験会にお越しください。
☑ 特性による「生きづらさ・働きづらさ」を感じている
☑ 就労移行支援にすでに通っているが不安や不満がある
☑ クローズ(障害者雇用枠以外)就労を目指したいが、特性への自己対処に自信がない
そんな不安や悩みを抱えている方は、ぜひ、お気軽にご連絡ください。
ディーキャリア芝浦オフィスでは、
障害者雇用枠を目指したい方はもちろん、
一般雇用枠での就職を希望されている方へのサポート
も積極的におこなっています。
「自分らしく働きたい」
そんなあなたのサポーターになれることを、スタッフ一同、心待ちにしています!
また、「発達障害の当事者座談会」を毎月開催中です。
詳しくはこちら>
フォームでのお問い合わせは
こちら >
ディーキャリア芝浦オフィスの紹介ページは
こちら>
お電話(03-6809-6985)やメール(job_info@happy-terrace.com)での
お問い合わせも受け付けております。