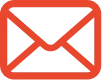ソーシャルスキルについて~発達障害との関連性と必要性について~
みなさん、こんにちは!!
ディーキャリアワーク柏スタジオです🙋
皆さんはソーシャルスキルという言葉を聞いた事がありますか?
発達障害当事者の方やデイケア、カウンセリングなどの利用経験がある方は
聞いた事があるかもしれません。
このソーシャルスキルは障害の有無に関わらず、
生活や働くの中で使う必要なスキルとされています。
しかし発達障害や、精神疾患がある事でこのソーシャルスキルを
身につける為の経験が少なかったり、理解しにくかったりする事があります。
今日は、ソーシャルスキルとは何か、就労移行支援事業所で実際にやっている
ソーシャルスキルトレーニングについて話をしたいと思います。

【ソーシャルスキルとは】
皆さんは友人の作り方、問題が起きた時の解決の仕方、
辛い時の逃げ方や対処方法などいつ誰から教わったか覚えていますか。
そしていつ頃から自発的にできるようになりましたか?
明確にいつ教わった、できるようになったと答えられる人は少ないと思います。
それは私たちが他者と関わる社会(家族、学校、会社など)の中で他者と関わり、
身につけているものだからです。

世界保健機関(WHO)では、ソーシャルスキルを具体的に
意思決定能力
問題解決能力
創造的思考
批判的思考
効果的なコミュニケーション
対人関係スキル
自己意識
共感
情動への対処
ストレスへの対処
と定義しています。
このソーシャルスキルは「ライフスキル」「社会技能」などと呼ばれることもあります。
簡単に表現すると対人関係の構築や維持、課題解決、
体調の維持の為に必要となるスキルと言えます。
このソーシャルスキルには満点、合格点というものはなく、
生涯を通して身につけていくものです。
対人関係や集団行動など日常のあらゆる課題は、
場面や状態が毎回さまざまで、その都度対応が異なり、
過去の経験の応用や臨機応変さが求められるので
「これくらいあれば十分」という風にはなりにくい為です。
【ソーシャルスキルを獲得しにくいケース】
ソーシャルスキルを獲得しにくい要因としては、
①特性によるもの
②間違った学習によるもの
③まだ学習していない
に大きく分けられます。
①の特性によるものとは、例えば発達障害の特性上客観的な視点が持ちにくい為、
スキルが身につきにくい、衝動的な行動によりスキルを獲得できる場面を
逃しているなどが考えられます。

②の間違った学習に関してですが、相手に自身の感情をぶつけ自身の要望を押し通す、
無理をしてしまい体調を崩す、問題から逃避し他の問題が起きるなどを
習慣的におこなってしまう事を指します。
③のまだ学習していないとは、例えばASDの方の場合興味の偏りにより
他者との関わりを持つことが少ない、他者を観察し学習しにくい、
あるいはスキルを獲得できる場面を苦手と感じ
極端に避けてしまう事で経験が少なく結果獲得していない事が考えられます。