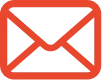記事一覧

ADHD当事者の筆者が、診断を受けたあとの行動ステップ、利用できる制度、職場への伝え方、自己理解・特性への工夫までを解説します。
- タグ:
- 合理的配慮
- 就労移行支援事業所
- 障害者雇用
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)

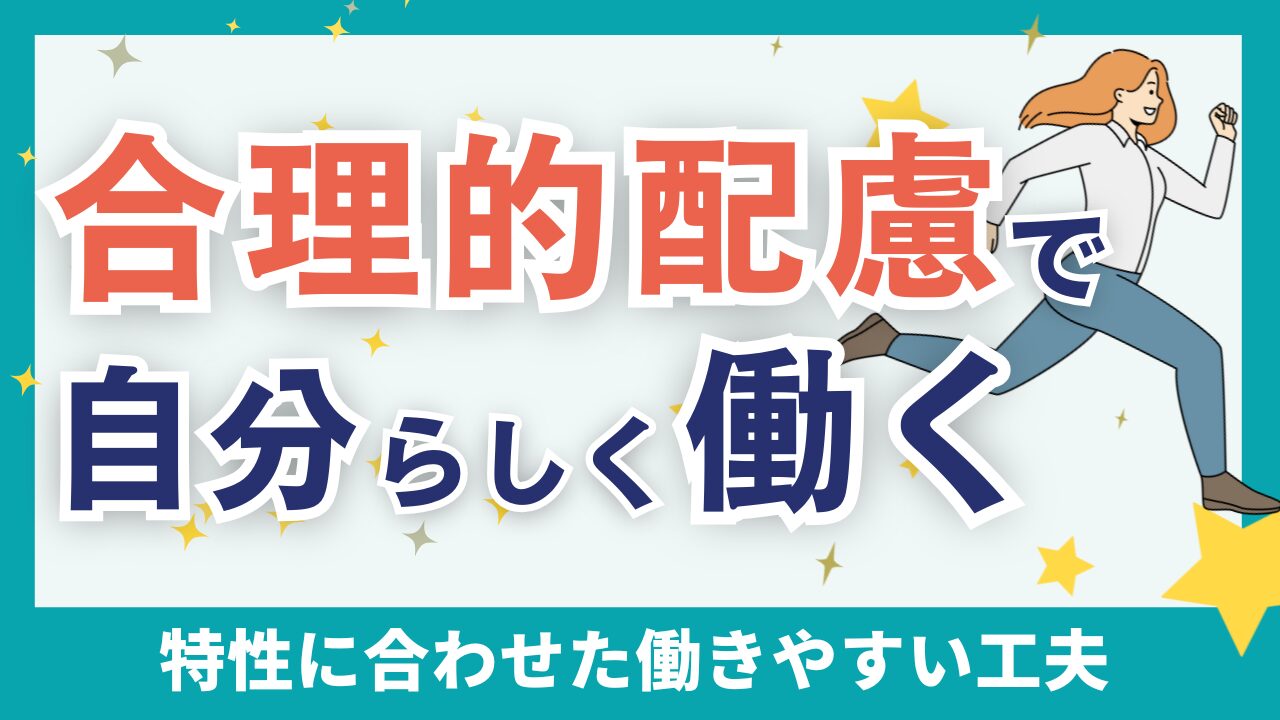
2024年4月から職場での「合理的配慮」が法的義務になりました。自分らしく無理なく働くためには、自分に合った配慮を見つけることが大切です。
- タグ:
- 合理的配慮

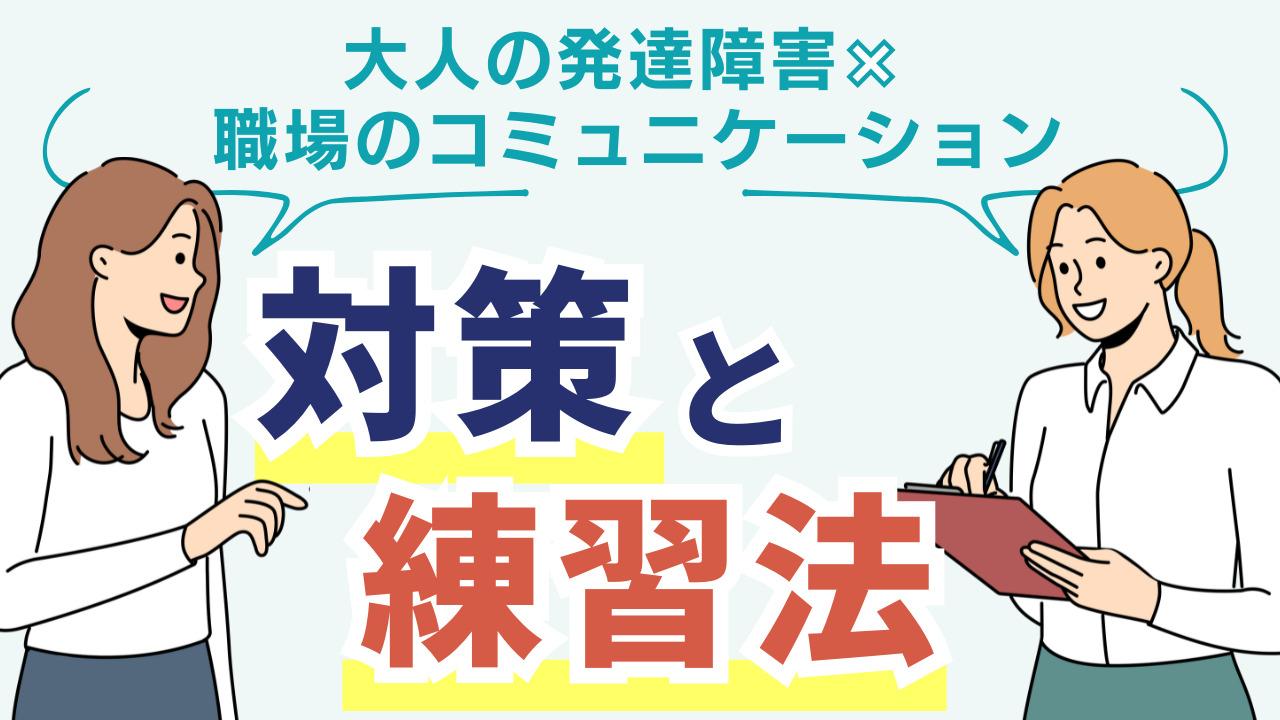
「職場でのコミュニケーション課題」について特性に応じた対策や練習法を紹介。ストレスを軽減し、自信を持って働くためのヒントをお伝えします。
- タグ:
- 合理的配慮
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)


就活がうまくいかず250社落ちた経験のあるADHD当事者が、失敗から学んだ対策法について紹介します。特性理解がポイントです!
- タグ:
- 合理的配慮
- クローズ就労
- オープン就労


障害者雇用と一般雇用の両方で就労経験がある筆者が、自身の体験談を交えながら、障害開示をするメリットとデメリットをお伝えします。
- タグ:
- 合理的配慮
- 障害者雇用
- クローズ就労
- オープン就労

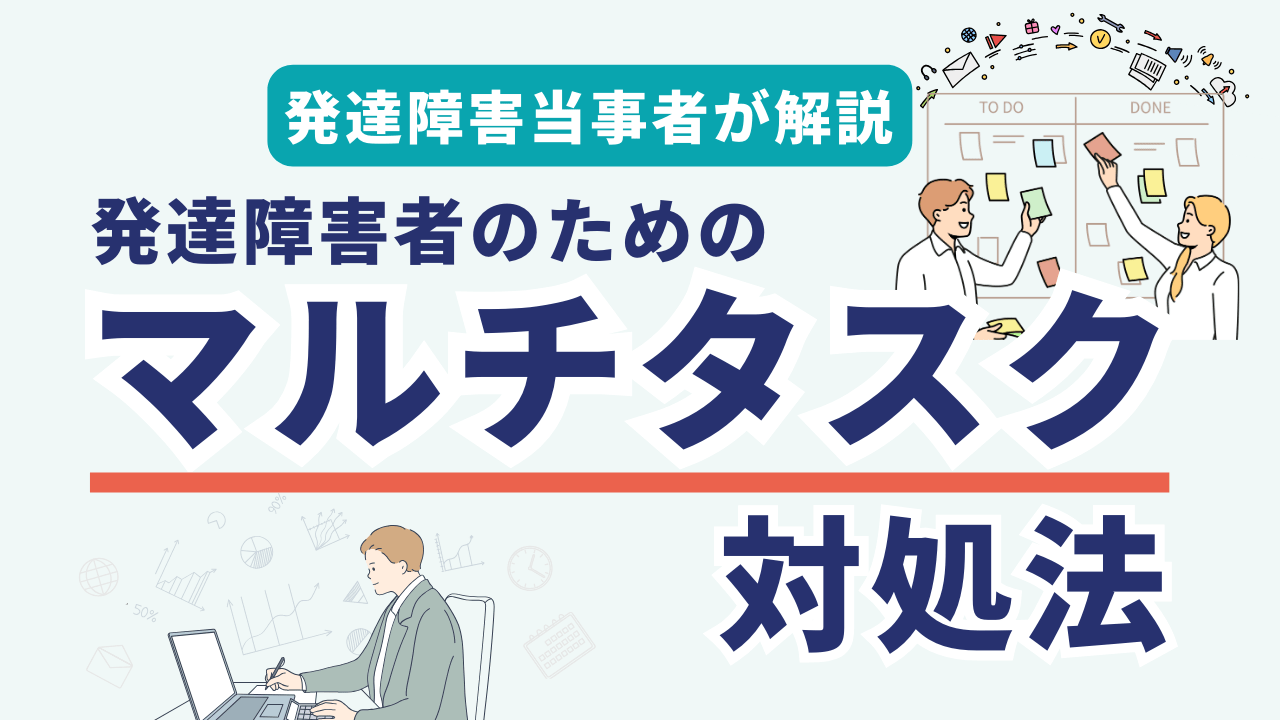
マルチタスクに苦手意識のあった発達障害当事者が、特性をカバーするために編み出した「タスク管理」テクニックを紹介します。
- タグ:
- 合理的配慮
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)


「仕事がうまくいかない…」を乗り越えるための対策を筆者の実体験をまじえご紹介。対策を立てた後に『継続』するためのコツもお伝えします。
- タグ:
- 合理的配慮
- 障害者雇用
- クローズ就労
- オープン就労
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)


長く健康的に働き続けるためにはどうすればいいのか。筆者の体験談を交えながら、なぜ発達障害のある方は仕事が長続きしない傾向にあるのか、その原因や対策などについてお伝えします。
- タグ:
- 合理的配慮
- 障害者雇用
- クローズ就労
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)


ASDのある方が困りごとを感じやすい「職場でのコミュニケーション」。筆者の体験談を交えながら、職場を安心できる居場所とするためのコツをお伝えします。
- タグ:
- 合理的配慮
- 障害者雇用
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


発達障害の特性により「職場でのコミュニケーションが苦手」という方に向け、実際に提供されている合理的配慮事項と自己対処法をセットで紹介します。
- タグ:
- 合理的配慮
- 障害者雇用
- オープン就労