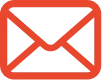記事一覧

ADHD当事者で抑うつ状態を経験した筆者が、特性による「働きづらさ」と二次障害である「うつ」を乗り越えるためのヒントを紹介します。
- タグ:
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


発達障害の治療法には服薬と心理療法があります。服薬の体験談と効果についてインタビューしました。薬に頼らず自己対処をすることも大切です。
- タグ:
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


発達障害のある方が心身健康に働くためには「自分に合う医師の選択」が重要です。実体験をもとに医師選びのポイントを紹介します。
- タグ:
- はたラクHACK
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


ASDのある方が困りごとを感じやすい「職場でのコミュニケーション」。筆者の体験談を交えながら、職場を安心できる居場所とするためのコツをお伝えします。
- タグ:
- 合理的配慮
- 障害者雇用
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


「自分に合った職場を選びたい」発達障害のある方が就職・転職時に求人検索をするときのチェックポイントを、当事者の体験談を交えてご紹介します。
- タグ:
- 障害者雇用
- クローズ就労
- オープン就労
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


発達障害当事者が押さえておきたい法改正のポイントを紹介します。今回は「障害者雇用率」と「就労選択支援」について分かりやすく説明します。
- タグ:
- 障害者雇用
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


「発達障害の特性による困りごとが性別で違う?」そんな疑問について解説します。性別による「区別」ではなく「違い」を知ることで、特性理解が深まり対策が立てやすくなります。
- タグ:
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


発達障害の当事者の皆さんが「カミングアウト」を実際にどうしているのか、そして障害のことを理解してもらうためにどうすれば良いのかについて、当事者の方へのアンケートや、同じく当事者である筆者の体験談を交えてご紹介します。
- タグ:
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


健康で長く働いていくためには、ストレスをうまくコントロールすることが欠かせません。今回は発達障害のある方がなぜストレスを感じやすいのか、その原因と対策を解説します。
- タグ:
- 合理的配慮
- 就労移行支援事業所
- はたラクHACK
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)

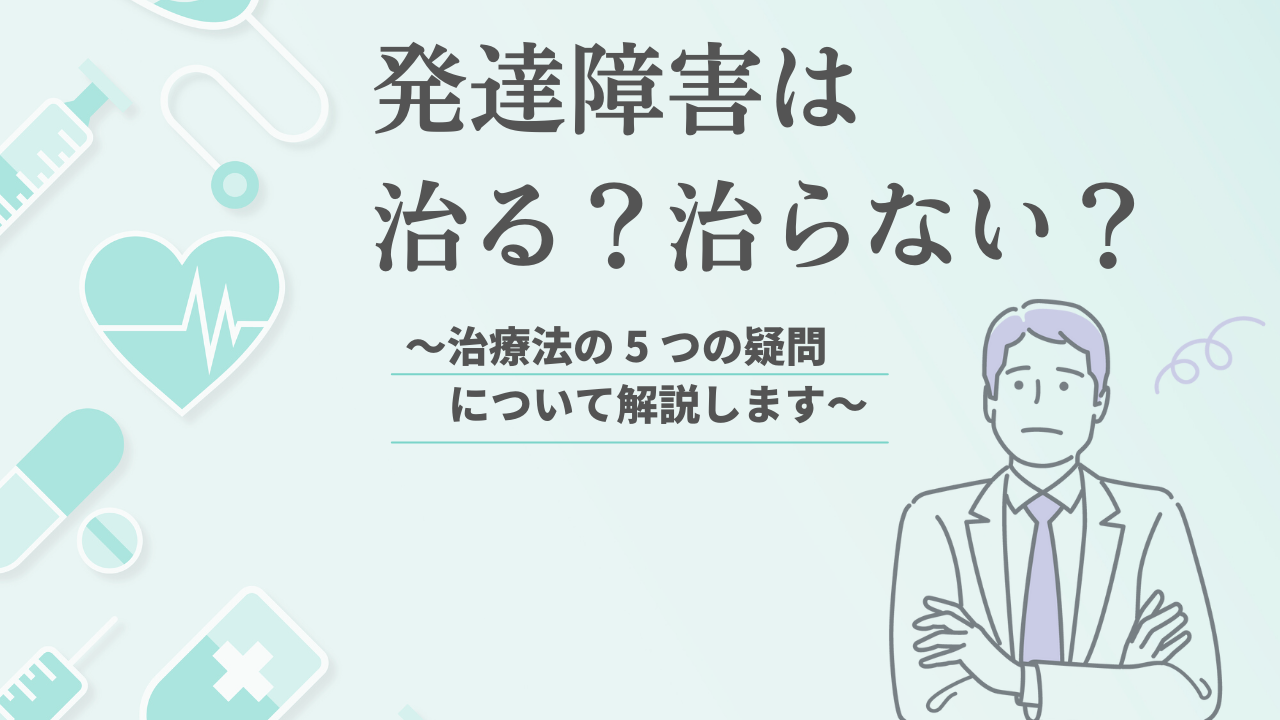
発達障害の診断を受けたあとはどのような治療を行うのか、症状は改善したり治ったりするものなのか。当事者の方や、サポートをされているご家族や同じ職場の方々にとっては、気になることではないでしょうか。今回の記事では発達障害の治療法に関する 5 つの疑問について解説します。
- タグ:
- 合理的配慮
- 就労移行支援事業所
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)