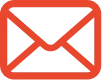発達障害と眠気の関係:なぜ眠くなるのか?対策は?
こんにちは!ディーキャリア秋田オフィスです。
春が近づいてきて暖かくなり、よく睡魔に襲われそうになる筆者ですが、発達障害(ADHD、自閉症スペクトラム障害〈ASD〉、限局性学習障害〈SLD〉など)のある方の中には、日中の強い眠気に悩まされる方が少なくありません。集中力の維持が難しい、過眠・不眠を繰り返す、あるいは睡眠の質が悪いといった問題が影響していると考えられます。本記事では、発達障害と眠気の関係について解説し、日常生活で実践できる対策を紹介します。
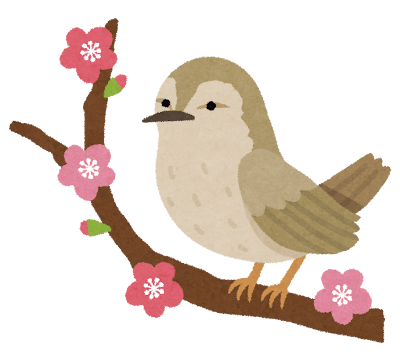
なぜ発達障害のある方は眠くなりやすいのか?
① 睡眠リズムの乱れ
発達障害のある方の特性の一つとして、体内時計(概日リズム)の調整がうまくいかないことがあります。特にADHDの人は夜更かししやすく、朝起きるのが苦手な「夜型」の傾向が強いです。その結果、日中の活動中に眠気を感じることが増えます。
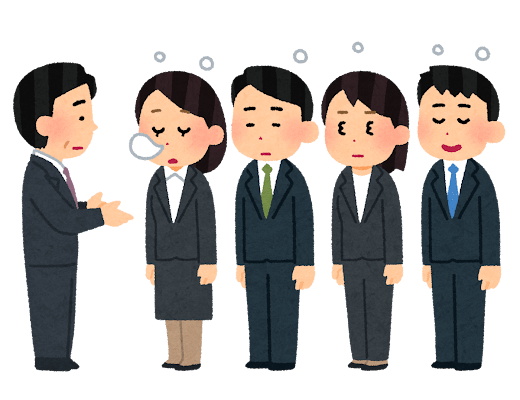
② 睡眠の質の低下
ASDのある人は感覚過敏の影響で、ちょっとした物音や光で目が覚めてしまうことがあります。また、ADHDのある人は「寝る直前まで頭の中が活発に働いている」ことが多く、寝つきが悪くなりがちです。こうした問題が積み重なることで、慢性的な睡眠不足になり、日中の眠気につながります。
③ 脳の覚醒レベルの不安定さ
ADHDのある人は「脳の覚醒レベル」が不安定で、過集中しているときは眠気を感じにくいですが、気が抜けた瞬間に強烈な眠気が襲ってくることがあります。また、一般的に退屈な作業(単純作業や待ち時間など)に弱く、その際に眠くなりやすい傾向があります。
④ 低血糖や栄養バランスの影響
発達障害のある人は、食事のタイミングが不規則になりやすいと言われています。特に、朝食を抜いたり、糖分の多い食事を摂ったりすると、血糖値の急上昇・急降下が起こり、眠気を引き起こします。
眠気対策のポイント
✅ 1. 規則正しい生活を心がける
・毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる
・朝起きたらすぐに日光を浴びる(体内時計を整えるため)
・寝る前のスマホ・PCの使用を控える(ブルーライトが睡眠を妨げるため)
✅ 2. 食事で血糖値を安定させる
・朝食をしっかり摂る(たんぱく質を意識する)
・甘いものを食べすぎない(血糖値の急変動を防ぐ)
・カフェインに頼りすぎない(カフェインが切れた後に眠気が増すことがある)

✅ 3. 眠気を感じたら短時間の仮眠をとる
・15~20分程度の仮眠が効果的
・長時間の昼寝は避ける(夜の睡眠に影響を与えるため)
✅ 4. 眠くなりにくい環境を作る
・温度調整をする(暖かすぎると眠くなりやすい)
・適度に体を動かす(軽いストレッチやウォーキングが効果的)
・単調な作業の合間に、刺激のある活動を取り入れる
まとめ
発達障害と眠気には深い関係があり、生活習慣や脳の覚醒レベルの変動が影響しています。眠気に悩まされている場合は、自分に合った対策を見つけることが大切です。まずは睡眠の質を改善し、日中の生活リズムを整えることから始めてみましょう!
------------------------------------------
本ブログは発達障害のある、就職された卒業生の方からの寄稿となります。
発達障害のある方、その傾向のある方、またそれ以外の方ももちろん、少しでも眠気や生活リズムに悩みを抱えている方のお役に立てましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
🐶🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🐶
◆ 見学・無料相談会 随時受付中です!
お悩みやご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。
🐶🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🐶
オフィスページ:就労移行支援事業所 ディーキャリア秋田オフィス
所在地:〒010-0001 秋田県秋田市中通1丁目3−5
電話番号:018-838-7010 受付(平日10:00~18:00)
Mail:akita@dd-career.com