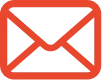記事一覧

ADHD当事者の筆者が、診断を受けたあとの行動ステップ、利用できる制度、職場への伝え方、自己理解・特性への工夫までを解説します。
- タグ:
- 合理的配慮
- 就労移行支援事業所
- 障害者雇用
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)

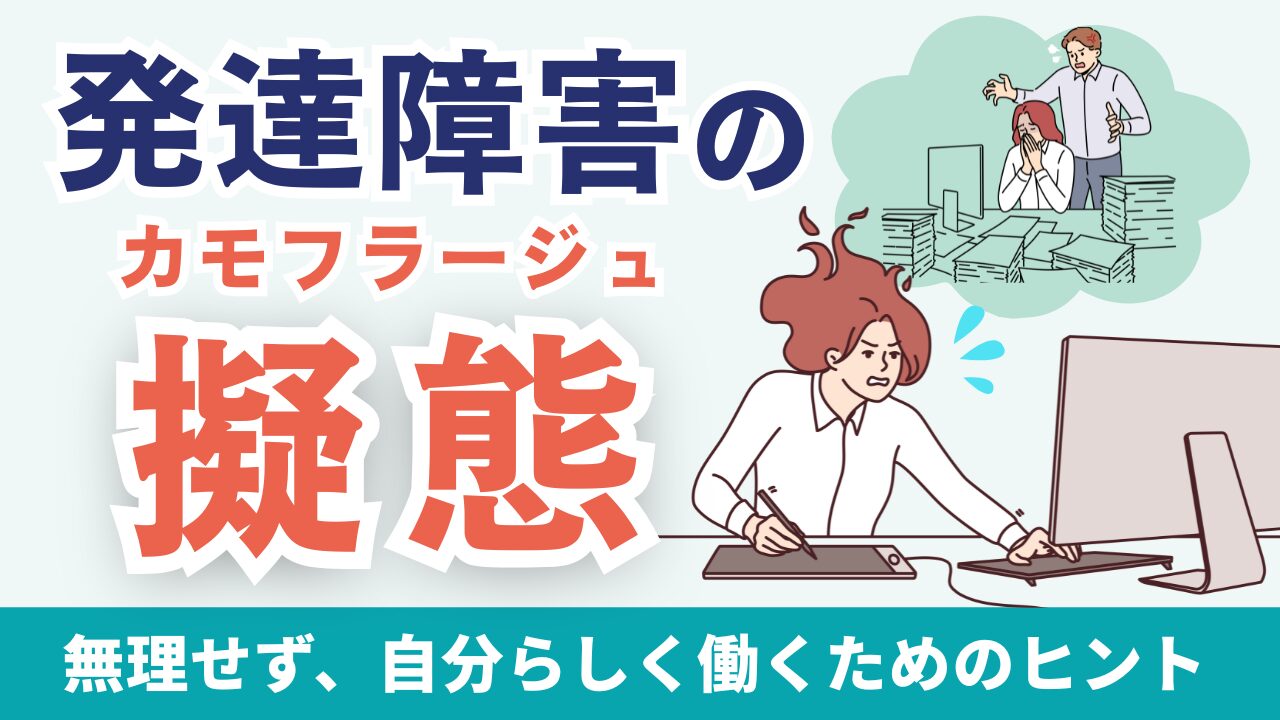
周囲に馴染むために本当の自分を隠そうとする「擬態」についてADHD当事者が解説。無理に特性を隠すことで起こるリスクや対処法について紹介。
- タグ:
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)


発達障害(ADHD/ASD)がある方の話し方の特徴、特性との関係性について解説 。発達障害当事者の実体験をもとにした対処法を紹介します。
- タグ:
- 就労移行支援事業所
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)


やめたくてもやめられない「リベンジ夜更かし」は、発達障害の特性が関係してる?当事者の経験に基づき、原因と対処法を分かりやすく解説します。
- タグ:
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)

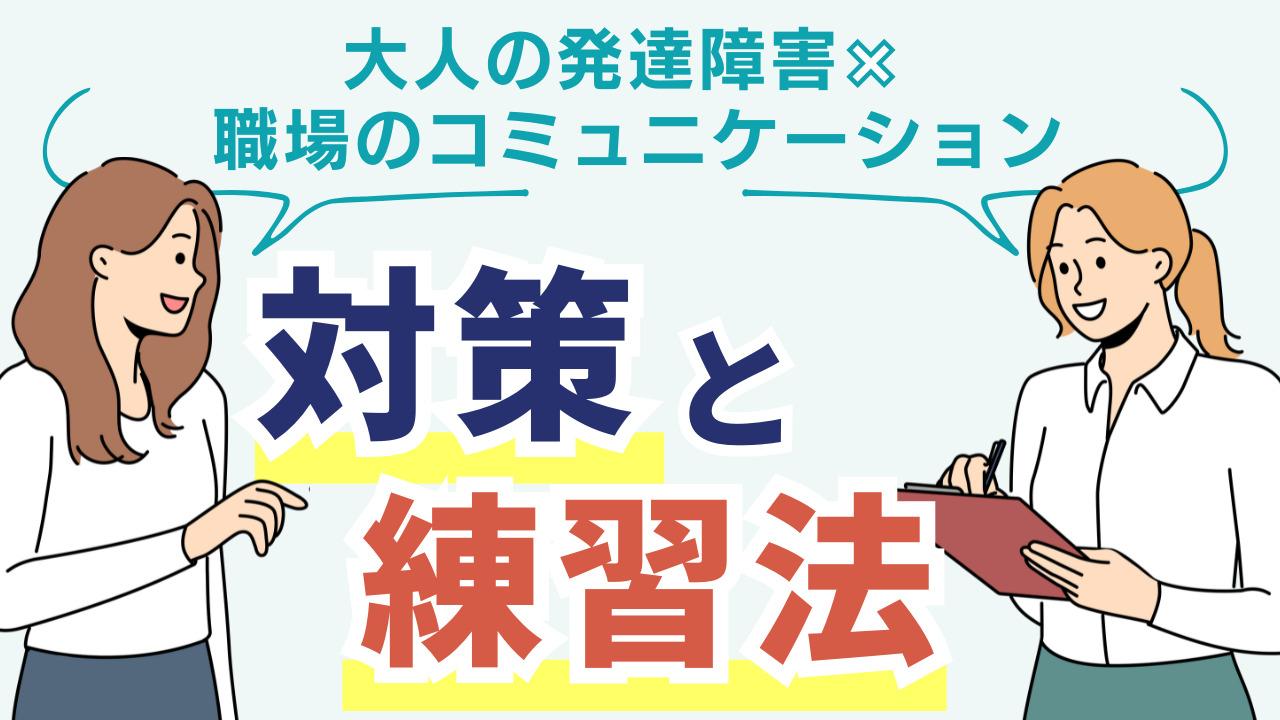
「職場でのコミュニケーション課題」について特性に応じた対策や練習法を紹介。ストレスを軽減し、自信を持って働くためのヒントをお伝えします。
- タグ:
- 合理的配慮
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)


ADHD当事者で抑うつ状態を経験した筆者が、特性による「働きづらさ」と二次障害である「うつ」を乗り越えるためのヒントを紹介します。
- タグ:
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)


金銭管理が苦手な発達障害のある方に向け、ADHD当事者が実際に効果のあった対策を紹介します。特性別の困りごとと支援制度についても解説。
- タグ:
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)


発達障害の治療法には服薬と心理療法があります。服薬の体験談と効果についてインタビューしました。薬に頼らず自己対処をすることも大切です。
- タグ:
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)

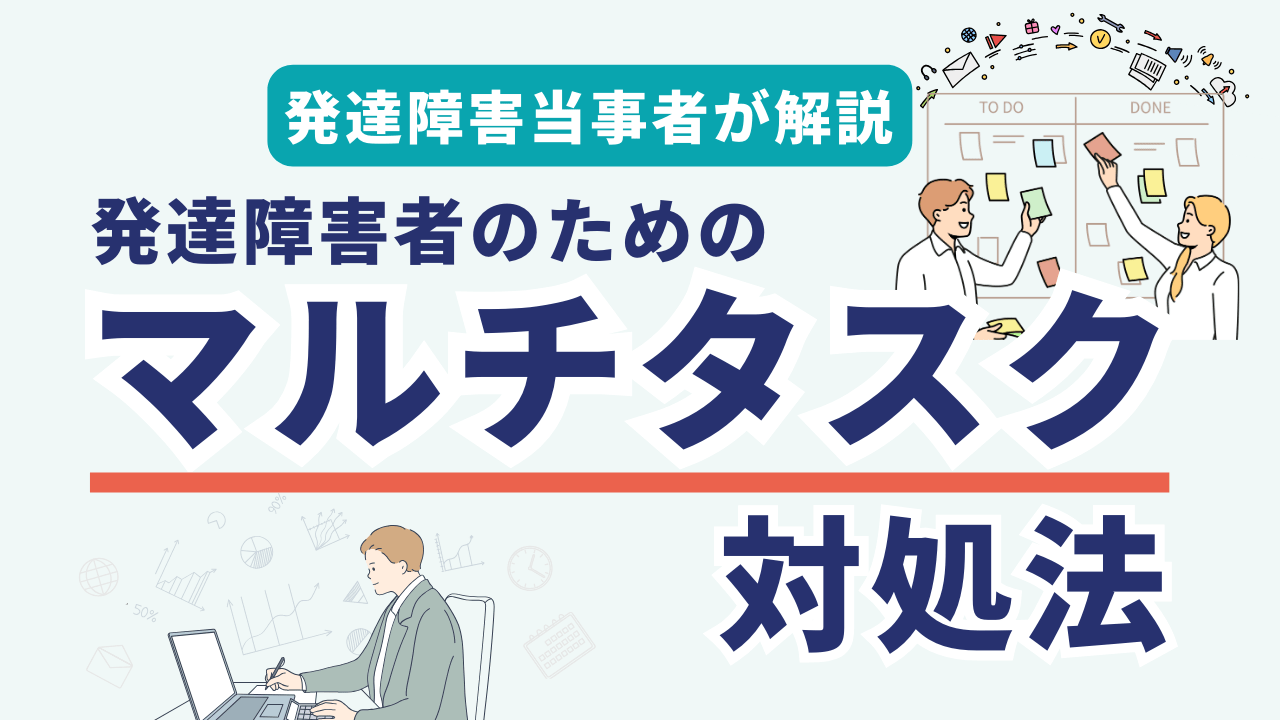
マルチタスクに苦手意識のあった発達障害当事者が、特性をカバーするために編み出した「タスク管理」テクニックを紹介します。
- タグ:
- 合理的配慮
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)


発達障害のある方が心身健康に働くためには「自分に合う医師の選択」が重要です。実体験をもとに医師選びのポイントを紹介します。
- タグ:
- はたラクHACK
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 限局性学習障害(SLD)