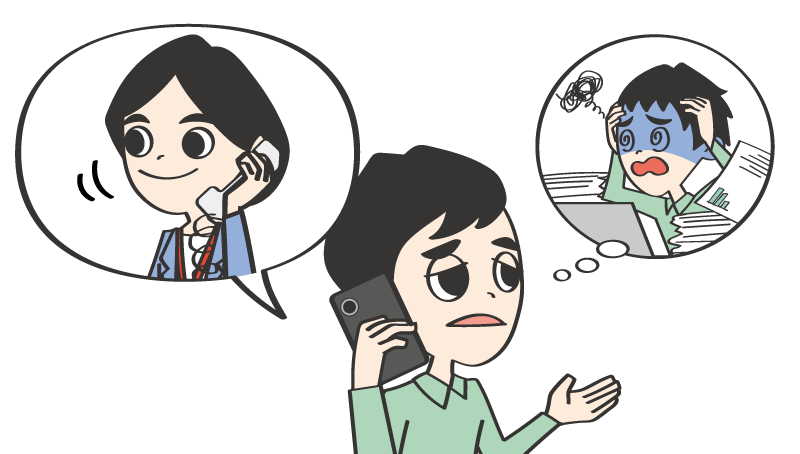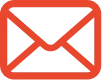ご不明点が解決しなかった場合、
お問い合わせフォームからお近くのオフィスにお問い合わせいただけます。
お電話(0120-802-146) でも承っております。
よくあるご質問
利用の流れは?
大きく5つのステップがあります。
STEP 1. お問い合わせ <お問い合わせフォーム>もしくは<お電話(0120-802-146)>よりお問い合わせください。
まだ診断が出ていない方も、お気軽にご相談ください。STEP 2. 無料見学・面談 ディーキャリアの事業所やプログラムの見学をすることができます。
まずは、ざっくばらんにお悩みごとやお困りごとについてご相談ください。STEP 3. 無料体験 ディーキャリアのプログラムに参加いただくことができます。
費用はかかりません。STEP 4. 利用契約(受給者証発行) お住いの自治体への「障害福祉サービス受給者証」発行に関わる申請など利用手続きのご案内をいたします。
ディーキャリアのスタッフが一連の流れを説明いたしますのでご安心ください。START. 利用開始 障害福祉サービス受給者証の発行が完了次第、利用をする事業所と利用契約をおこないます。
就労移行支援とは?
障害のある方の「働く」をサポートする障害福祉サービスです。(厚⽣労働省の許認可事業)
一人ひとりの「働く」に関する悩みや課題にあわせた支援をおこないます。- 障害特性との付き合い方を学ぶこと
- 働くための準備をすること
- 自分に合った職場を探し、就職活動をすること
利用料金はどのくらい?
就労移行支援事業所の利用料は、9割が国と自治体の負担、残りの1割が自己負担です。
さらに、世帯所得に応じて、「負担上限月額区分」が設定されており、1か月の利用日数に関わらず、
それ以上の負担は生じません。
ディーキャリア利用者の方のうち約8割程度の方が、自己負担額0円で通所されています。詳しくは「ご利用料金について」をご確認ください。
障害者手帳は必要?
障害者手帳は必須ではありません。
医師の「診断書」や「意見書」など、障害のあることを証明できる書類をご用意いただければ、自治体の判断により利用をすることができます。
利用時には「障害福祉サービス受給者証」の発行が必要です。
利用条件は?
下記3つの条件を満たす必要があります。
- 原則65歳未満の方※65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスについて引き続き利用することが可能
- 障害(精神障害、発達障害、身体障害、知的障害、難病)のある方
- 一般企業等(就労継続支援A型・B型など福祉支援のある事業所以外)への就職を目指しており、就職が可能と見込まれている方
障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の「診断書」や「意見書」など、支援が必要であることを証明できる書類をご用意いただければ、自治体の判断により利用をすることができます。
休職者、在学中の大学生(4年制大学・大学院・短大・高専含む)については、一定の条件を満たす場合に、ご利用いただけることがあります。- 原則65歳未満の方
一般雇用枠(クローズ就労)を目指すことはできる?
可能です。実際に支援実績があります。
一般雇用枠を目指す方に向けたサポートもおこなっております。一般雇用枠の中にも、障害を開示するオープン就労、障害を開示しないクローズ就労がありますが、いずれの支援実績もあります。
とくに障害を開示しないクローズ就労の場合には、就職先に合理的配慮の依頼をすることができないため、ご自身で特性対策やセルフケアをおこなわなければなりません。自己対処力を高めるプログラムも用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
どのようなサポートを受けられる?
発達障害・精神障害のある方が、長期的に社会で活躍することを目指す、就職“後”を見据えたサポートをおこないます。
①働くための準備をサポート・働くうえで必要となる知識・スキルを身につけるための訓練
・生活リズムを整える、体調管理やストレス対処法を身につけるための訓練
・職場体験、企業実習②就職活動をサポート・一人ひとりの適性や特性にあった働き方・職場探し
・求人の開拓・紹介、就職活動のフォロー(就職相談・面接練習・応募書類添削等)③職場定着をサポート・就職後、勤務継続するために必要な相談・支援をするための面談
・企業に対する職場環境調整の依頼
※就職後半年間、就職先での悩みや課題を解決するためのサポートを実施 7か月目以降は「定着支援サービス」を最長3年間利用可能働くうえでの「障害特性による苦手」を見極め、対処法を実践するための環境と、自身の障害特性への理解を深め、「働きづらさ」への工夫を習得するためのプログラムを用意しています。
どのくらいの期間利用できる?
原則最長24カ月(2年)ですが、自治体より必要性が認められると、更に最大1年間延長されることがあります。
利用期間は個人や事業所により差があります。ディーキャリアでは、平均すると10~12カ月です。
お問い合わせ